ミゲス: ヴァイオリンソナタ
ヴィラ゠ロボスがブラジルを代表する作曲家であることは論をまたないであろう。ではそれよりも前、ブラジルではどんな作曲家が活躍していたのだろうか。例えば1850年生まれのレオポルド・ミゲス。ヴィラ゠ロボスよりも一世代前の作曲家で、リオデジャネイロの国立音楽学校校長を務めた人である(後任はエンリキ・オスワルド)。その『ヴァイオリンソナタ』を収めたアルバムを聴いてみた。
Leopoldo Miguez: Violin Sonata, Op. 14
Emmanuele Baldini (vn)
Karin Fernandes (pf)
(2014)
4楽章の端正なソナタで、ヨーロッパのロマン派音楽の枠を踏み外さず、明朗な歌と素直な感情の起伏があり、気持ちよく聴くことができる。特に前半ふたつの楽章が良い。第3楽章はベートーヴェンが書きそうなスケルツォだが、そのトリオに何気ない感じでフガートを潜り込ませており面白い。また、このアルバムの美点は演奏もさることながら、そのプログラムにある。ミゲスのこのソナタを、ヴィラ゠ロボスよりも3歳だけ上のグラウコ・ヴェラスケス(Glauco Velásquez)の2曲の『ヴァイオリンソナタ』が挟み込むようになっている。ヴェラスケスのソナタは、構成が古典的で骨太のミゲスに比べて、繊細な響きを即興的・幻想的に操っている感じであり、こうして並べると両者の対比が際立ち、飽きさせない。とはいえ、どちらもヴィラ゠ロボスのような民族音楽的側面はなく、ヨーロッパのロマン派の技法に忠実な作品であり、この点で同時期のアメリカ・ニューイングランド楽派と似た状況だったのだろうと想像される。
ミゲスの『ヴァイオリンソナタ』は、以前ビーチの『ピアノ五重奏曲』の回で取り上げたSOMM Recordingsの"Treasures from the New World"シリーズの2作目にも入っている。
Leopoldo Miguez: Violin Sonata, Op. 14
Anthony Flint (vn)
Clelia Iruzun (pf)
(2019)
上のバルディーニ/フェルナンデスのNaxos盤に先に馴染んでいたせいか、最初は良い印象を抱かなかった。特に第1楽章、バルディーニの演奏より(ほんのわずかだが)遅めで、楽譜通りキチキチと拍を刻む感じが曲の弱点を露呈させているように聴こえた。この時はしかし音量設定が小さすぎだったのかもしれない。不思議なことに数回聞き返しているとそういった違和感はなくなり、味のある良い演奏に思えてきた。バルディーニが伸縮自在でかなり自由に歌うことを優先しているのに対し、曲そのままの姿を恣意的にいじることなしにどこまで美しさを表出できるかを追及しているという感じだろうか。
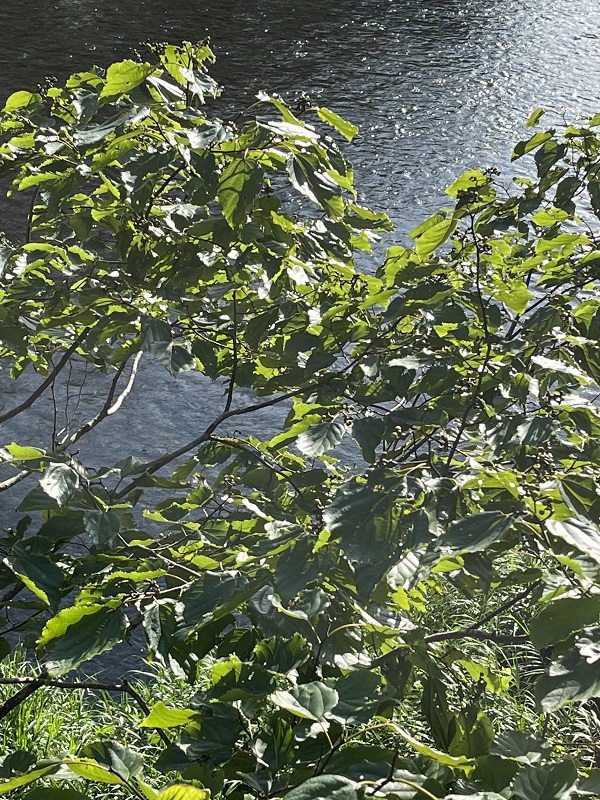
(Sep. 16, 2023)